特措法とは?クリニック経営する医師だけに認められたお得な税制
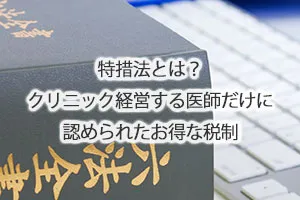
いずれ病院を退職して開業医を目指される先生には、ぜひとも知っておいてもらいたい法律があります。その法律を「特措法」といいます。
この法律を活用することで、税金の多くが免除されて、先生の手取り収入を大幅に増やすことができます。
この記事では、特措法とはどういった法律なのか、なぜ手取り収入を増やすことができるのか、特措法でお得になるための条件や特措法と相性の良い開業方法をご紹介いたします。
特措法とは?
クリニックを開業した先生にとってお得な特措法とは、正式名称は「租税特別措置法第26条」といいます。この法律は、「個人経営のクリニックの1年間の総収入金額が、保険診療報酬5,000万円以下で自費診療の収入が2,000万円以下であれば、その保険診療報酬の約70%を概算経費として認める」というものです。
条件にもよりますが、特措法を利用することで1年間の保険診療報酬の売上高を5,000万円以内に抑えることによって、手取り収入を最大3,000万円くらいにすることができます。
この条件については、後ほどご説明します。特措法の内容は、税務研究会ホームページ「租税特別措置法 第26条 社会保険診療報酬の所得計算の特例」をご参照ください。
特措法を利用したときの先生の手取り収入とは?
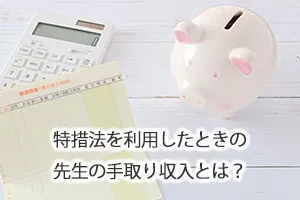
特措法を活用したときと、活用しなかったときの先生の手取り収入を試算したいと思います。試算の条件は、次のようなクリニックを想定します。
- ■ 1年間の売上高が5,000万円
- ■ 家賃や水道光熱費などで合計700万円
- ■ スタッフの人件費が800万円
- ■ 変動費が10%として5,000万円×10%=500万円
変動費とは、患者さんの来院数に応じて変動してかかる経費のことです。例えば、医薬品やディスポの診療材料などの医療消耗品が変動費になります。それに対して、患者さんの来院数が増減しても変動しない固定費というものがあります。家賃や水道光熱費、スタッフの人件費は、患者さん数にほとんど変動せずに毎月一定の金額がかかるので、これらは固定費に当たります。
特措法を利用した場合の概算手取り収入
まず特措法を活用すると、5,000万円の売上高のうち、約70%が経費として認められます。すると、税務申告のときに「5,000万円の70%である3,500万円が経費としてかかった」と申告できます。しかし、実際にかかった経費は、合計2,000万円です。申告をした3,500万円と実際にかかった経費2,000万円の差額は、1,500万円です。まず、この1,500万円を先生の手取り収入にして良いということになります。
次に、申告をする利益は、5,000万円から概算経費3,500万円を引いた、1,500万円となります。この1,500万円に所得税や社会保険料などがかかってきて、残りが約1,100万円になります。これが第二の手取り収入となります。
そして先生の年間の手取り収入の合計は、概算で1,500万円+1,100万円=2,600万円/年になります。
特措法を利用しなかった場合の概算手取り収入
次に特措法を利用しなかった場合の手取り収入を概算したいと思います。5,000万円の売上高のうち、実際にかかった経費は2,000万円です。そして、税務処理をするために会計士さんや税理士さんに依頼をすることになるので、余分に100万円ほどかかります。すると、経費は2,100万円です。
5,000万円から2,100万円を引いた利益は、2,900万円になります。これに所得税や住民税・社会保険料などがかかってきます。すると、手取り収入は約2,000万円弱になります。
特措法を利用したときの手取り収入は約2,600万円、特措法を利用しなければ約2,000万円弱となり、特措法を利用するとおよそ600万円から1,000万円くらいはお得になります。
特措法を活用しない青色申告の実額経費で確定申告して、手取り収入を3,000万円くらいにしようと思うと、売上高を9,000万円~1億円くらいまで増やさないといけないため、特措法を活用するときよりも2倍くらい働くことになります。クリニックの診療単価は診療科目によってだいたい一定していますから、2倍の売上高を得るためには2倍の患者数を診なくてはなりませんので、それだけ多くのスタッフを抱えないといけないため、家賃や人件費などの固定費も多く出ていくことになり、リスクの高い経営になってしまうのです。
なぜこのような個人経営のクリニックにお得な法律があるのか?
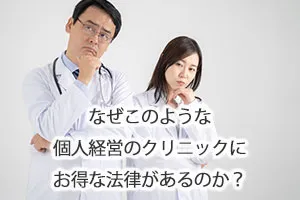
特措法が生まれた経緯
1958に国民健康保険法が制定されて、1961には国民皆保険が実現されて現在の健康保険制度に繋がって行きました。当時、開業医の団体である日本医師会は、診療報酬の値上げを強く要望していましたが、まだ国の財政が厳しい時代でもあったために、それが出来ずにいました。制度としての診療報酬を上げることで、国民医療費全体が膨大に増えてしまうことを恐れていたからです。
そこで、日本医師会を中心とした開業医に対して、保険診療で売り上げた金額の7割くらいを必要経費として認めるということで、日本全国の国民医療費を上げることを防ぐ目的で、開業医である医師会の会員に対する反対給付として特措法が生まれました。実際にクリニック経営にかかった経費が2割くらいであれば、実質的には5割くらいの売り上げを申告しなくても良いというような、特別扱いの税金の制度が作られたのです。
この制度ができた当初は、保険診療に対する売上の限度はなくて、総売上の7割くらいを経費として認めてもらえるので、残りの3割を収入として申告して税金を払えば済みました。
こうした制度のおかげで、昔の開業医は売上の半分以上を手取り収入として残すことができたので、現金預金がかなり貯まったのです。
そのうちに、「この手取り収入の高さは行き過ぎではないか?」と税制に関する不公平感が国会でも問題視されるようになり、売上の上限金額を設定されるようになり、現在では社会保険診療報酬が5,000万円以下でないと特措法が活用できないように法改正されました。
特措法によりクリニックが身近になった
特措法があったおかげもあって、日本の至る所に診療所ができ、今では過当競争とまで言われるようになりました。しかし、医療を受ける側からすると、クリニックの選択肢が増えて競争原理が働くようになったため、サービスの良いクリニックが増えたと思います。
当社にてご支援させていただいている先生には、「患者さんに対して丁寧に診療する先生は、近所でも評判になって経営が安定するようになります」とアドバイスさせていただいています。反対に雑な診療をする先生だと、すぐにネットで悪い口コミが書かれてしまって、クリニックの評判を下げてしまうことになり、評判の良いクリニックに患者さんを取られてしまい経営根も行き詰まってしまいます。
クリニックが増えて競争原理が働き、良いクリニックが残っていくということは、社会にとっても良いことだと思います。
特措法と相性の良い開業医のワークライフバランス
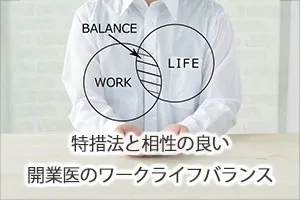
開業医にとって特措法は、手取り収入が増えることになり、とてもお得なように思えるかもしれませんが、診療報酬の上限が5,000万円ということが条件になりますので、バリバリと働きたい先生からすると物足りないかもしれません。
しかし、先ほどご説明したように、1億円ほどの売り上げになるように働いてやっと手取り収入が3,000万円ほどになることを考えると、売上高を5,000万円に押さえておいて、自由な時間を増やしながら、手取り収入もしっかりと確保のできる方がお得のように感じます。特措法を活用することは手取り収入を増やしながら自由時間が増えることを意味します。
この税制をうまく活用できれば、次のようなワークライフバランスをお考えの先生にはとても相性の良い開業方法であると言えます。
- ■ 子育てとキャリアを両立させたい
- ■ 定年退職後も開業して医師としての仕事を続けたい
- ■ 患者さんのために時間をかけた診療を行いたい

子育てとキャリアを両立させたい
特措法は、子育てとキャリアを両立させたい女性医師におすすめです。子育てをして中学受験の頃になると、母親は何かと学校に呼び出されたり、子どもの面倒を見たりと忙しくなります。中学受験は親の受験とも言われるように、親が子どもの世話をどれだけしたかによって、受験の勝敗も左右されると言われています。
子育ての時間をなるべく多く取りたい場合は、もちろん勤務医では難しいことでしょう。また、クリニックを開業するとなると余計に自由に休めないように思えるかもしれません。でも、クリニックを予約制にすることで、ご自身の仕事の時間を自由に調整することができます。お子さまの授業参観の日や、塾の面談の日にはクリニックの予約を入れないようにしておくことで、自由に休みを取ることができます。
特措法を活用すると、売上高を5,000万円以下にしないといけませんから、時々休んで売り上げを調整するくらいの方が、クリニック経営にとっても都合が良いわけです。
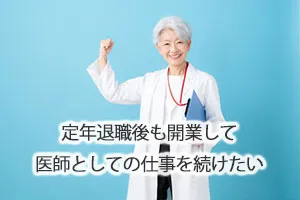
定年退職後も開業して医師としての仕事を続けたい
当社に大学に勤務している医師から「定年退職後も開業して医師としての仕事を続けたい」というご相談をいただき、開業のご支援をさせていただきました。特措法を活用した開業方法は、定年退職後の低リスク開業にも最適です。
子育てと同じく、定年退職後の自由なライフスタイルを送る時間を確保しながら、ミニマム開業で予約制の診療を続けることで安定した老後の生活を送ることができます。そうした場合にも集患のしやすい人通りの多い場所で開業することをお勧めします。

患者さんのために時間をかけた診療を行いたい
病院での勤務医のときに、患者さんを流れ作業のように診ていて、「もっと患者さんとコミュニケーションを取りながら診療をしたい」とお考えの先生もいらっしゃいます。そのような先生にも特措法を活用した開業方法は最適です。
診療時間をかけることで、評判の良い先生になりますが、1人当たりの診療に時間がかかるので1日に診られる患者さんの数が限られてきます。すると、特措法の上限以内で売上が収まりますのでこれも都合が良いわけです。
患者さんの数が他のクリニックと比べて比較的少人数であっても、先生の手取り収入が増えて、経営が安定して人気のクリニックになることでしょう。
特措法を活用して手取り収入を増やすコツ
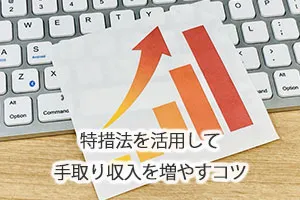
最後に特措法を活用して、手取り収入を増やすコツをご説明いたします。
特措法は、診療報酬の約70%を概算経費として認められるわけですが、手取り収入を増やすためには、実際にかかる経費をできるだけ少なくして、概算経費との差額を大きくすることが大切です。ですので、特措法を活用して出来る限り手取り収入を増やす方法というのは、出来る限り必要な実額の経費を減らすという方法です。
出来る限り経費を減らし、手取り収入を最大限に増やすことで、クリニックの経営はとても安定するわけです。ではどのような経費を減らすのかというと、次の2種類に集約されます。
- 1.テナントの家賃
- 2.スタッフの人件費
この2つの経費が、クリニック経営における最大の固定費となります。テナントの家賃を下げる方法は、家賃の安いところに入居することなのですが、単に家賃が安いところに入居するだけでは、本末転倒になりかねません。その理由は、家賃が安いところは集患がしにくい立地条件の悪い場所である可能性が高いからです。
もし集患がしにくい場所であれば、必要な経費を下げられたとしても売上も下がってしまうので、結局は経営が不安定になってしまうことを意味します。
「ではどうするのか?」ということですが、それは坪単価の高い人の集まりやすい場所の物件で、なるべく坪数の小さいテナントを借りることです。そのためのポイントとしては、スタッフの休憩室などの2次的な用途のスペースを取るのを止め、医療機器は必要最小限に抑えることです。すると、立地条件の良い場所を割安で借りることができます。
このことは、人件費の削減にもつながります。休憩室が必要ないくらいの人数に押さえ、予約制を導入することで、受付にパート勤務のスタッフを1名ほど配置するようにします。事務長や常勤スタッフ、経理担当などは雇いません。なるべく人を雇わないで人件費を抑えるようにします。
特措法を活用すれば、概算経費が認められますから、領収書を集めて税理士さんに依頼して帳簿を作る必要もなくなります。
以上、特措法とはどういった法律なのか、特措法を活用して先生の手取り収入を増やす方法、特措法と相性の良い開業方法、出来るだけ先生の手取り収入を増やす方法をご説明いたしました。まとめると、診療報酬を5,000万円以下に抑え、できるだけ経費をかけないようなクリニックにして、予約制にすると、先生は時間的な余裕を持って働きながら手取り収入を最大3,000万円ほどまでにできます。
これから開業を目指されている先生で、特措法を活用した開業方法で事業計画を立てたい場合は、支援実績多数のオクスアイにお任せください。東京23区やその周辺都市にて、子育てと開業を両立させたい、定年退職後に開業して医師としての仕事を続けたいといった先生など、当社は多くの特措法を活用したクリニックの開業をご支援してきた実績があります。
特措法を活用した開業をお考えであれば、まずは当社で行っている無料のWebセミナー&相談会にご参加ください。このセミナーでは、時間に余裕を持った働き方をしながら先生の手通り収入を増やせる特措法の活用方法をご説明しつつ、開業によって先生が実現したい将来設計などのご相談にも対応しています。
安心して開業したい先生からのご相談をお待ちしております。



