医師が開業で失敗しやすい典型的パターンとその対策方法とは?
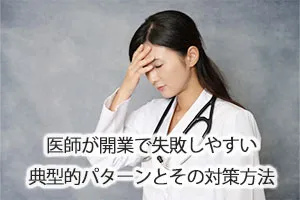
病気の治療にはセオリーがあるように、クリニック経営にもセオリーがあります。これから「勤務医を辞めて開業したい」とお考えの先生に向けて、医師が開業で失敗しやすい典型的なパターンと、その対策をご説明いたします。
最初に述べておきたいことは、クリニック経営での失敗は、「入ってくるお金よりも、出ていくお金が多いことが続くこと」によって起きます。入ってくるお金と出ていくお金を全方位的に検討して事業計画を立てることが、クリニックの開業準備で大切なことです。
入ってくるお金とは、患者さんを診療して得られる診療報酬のことです。出ていくお金とはクリニックを運営することで出ていく経費のことです。経費には、診療した患者さんの人数に応じて比例する「変動費」と、患者さんの数に関わらず一定の金額が出ていく「固定費」があります。
クリニックの安定経営では、『診療報酬>(固定費+変動費)』とすることが基本となります。そのプラスになった金額を、先生の手取り収入として生活費や借入金の返済に充てることができるわけです。
このように、クリニックに入ってくるお金や出ていくお金の予想は、全方位的に検討する必要があります。しかし、依頼する開業コンサルタントによっては、知識不足によってこれからの時代に合った検討ができない人もいますので、ご注意ください。
それでは、典型的な失敗パターンとその対策を、一つずつご説明していきます。失敗しない低リスクなクリニックを開業したい先生は、最後までしっかりご覧ください。
自己資金がゼロ円で失敗

最初の失敗談は、自己資金についてです。開業コンサルタントによっては、「自己資金がゼロ円でも開業ができる」と言う人もいます。確かに、自己資金がゼロ円であったとしても、開業ができることは、嘘ではありません。
なぜ自己資金がゼロ円だと失敗しやすいのか?
自己資金がゼロ円であった場合には、集患がしやすい立地条件の良い場所をすぐに借りることが難しい場合があります。良いテナントが見つかったとしても自己資金が無い場合には、すぐに契約することができないので、ほかの人に先を越されて良い場所を借りることが難しくなり、経営リスクが高まることが多いのです。
立地条件の良い場所とは、集患がしやすい場所ですから、患者さんが多く来院してくれるようになり、診療報酬も得やすくなります。そういった場所は、クリニックに限らず、他の業種の人たちも借りたい物件になるため、テナント獲得の競走が激しくなります。
テナント物件の契約は、初めに物件を借りるための申し込みをするわけですが、早く申し込んだ順に審査を受ける権利がありますが、審査に通った後は「すぐにテナント契約に必要な契約金を払える人」がテナントを獲得することになります。
大家さんとしては、クリニックに入ってもらったら長期間にわたって入居してもらえることが多いので、安定的な収益につながります。しかし、「自己資金を持っていない」という人にテナントを貸すことは、少し躊躇するかもしれません。なぜなら、世間的には「お医者さんは高収入」ということになっているので、「それなのに自己資金を持っていないということは、貯金のできないお金にルーズな人だ」と思われてしまう場合があります。大家さんとしては、毎月しっかり家賃の支払いをしてくれる金銭感覚のキチンとした人に貸したいわけです。
テナント契約をするときには契約金として、1ヶ月分の前家賃と仲介料+保証会+礼金+保証金などが5~10ヶ月分程度必要です。すぐにお金が欲しいと考えている大家さんであれば、すぐに家賃や保証金などを含めた契約金を払ってくれる人に貸したいわけです。
自己資金は500~1,000万円を用意しておくこと
このようなことから、将来的に開業を検討していて、「集患がしやすい場所にクリニックを開業したい」とお考えの場合には、少なくとも自己資金を500万円~1,000万円ほど貯めておいてください。自己資金の目安は、都心での開業を検討しているのであれば1,000万円ほど、郊外であれば500万円程度あれば良いと思います。
立地条件の良いテナントを発見したら、すぐに開業コンサルタントと確認をしに行きます。そして、開業コンサルタントが今までの経験から「ここなら良い」と判断されたら、すぐにテナント契約に進むことができます。
大家さんに「自己資金ですぐに契約金を用意できます」と伝えたら、テナント契約が結びやすくなります。また、自己資金があればその先の融資契約にも有利になりますので、気持ちに余裕も出て、あせって契約をすることを防ぐこともできます。
高額な医療機器を導入して失敗

高額な医療機器を導入すると、借金の金額が大きくなり、また医療機器を操作するためのスタッフも多く雇い入れて固定費が増大し、失敗するケースがあります。高額な医療機器を導入したクリニックのことを、当社では「重装備開業」と呼んでいます。
焦って開業して重装備になり失敗
勤務医をされている先生によっては、「すぐにでも病院を辞めて開業をしたい」とお考えの方もいらっしゃることでしょう。40代になられてから管理職という職責を担い、若手の先生方を早く帰宅させて、自分だけ居残りをするような方もいらっしゃいます。そういった先生から、「勤務医では身体がもたない」ということで、当社に開業相談をいただくこともあります。
そういった先生は、病院を辞めて、他の病院に転勤したとしても、また同じような環境で働くことになる可能性もあるので、「早く独立して、自分の好きなように仕事をしたい」と考えるわけです。
クリニックを開業するときには、自分が専門とする診療科目で開業しますが、診療科目によっては、冒頭で解説した固定費が大きくなりやすいものもあります。また、「自分の思い通りのクリニックにしたい」ということで、高額な医療機器を導入してしまう先生もいらっしゃいます。
固定費が大きくなる診療科目のクリニックや、高額な医療機器を導入する必要のあるクリニックでは、当然ながら借入金の金額も大きく膨れ上がります。すると、高額な借金返済のために、先生は今まで以上に熱心に働くことが求められる場合もあります。
開業した当初は、「これで自由に働くことができる」と思い、気持ち良く働くことができるようになることでしょう。しかし、2~3年も経過した頃に、借金返済の重圧で、借金返済のために働いているような気分になり、「独立しない方が良かった」と考えるようになりかねません。
クリニックで手術ができる設備を導入して失敗
勤務医のときに手術をバリバリやられていた先生に多いのですが、独立してクリニックを開業したときに、「勤務医のときに行なっていた手術を、クリニックでも同じように行えるようにしたい」というご要望をいただくことがあります。
手術の設備を備えたクリニックは、かなりの確率で失敗しやすいです。その理由は、ここまでご覧になられた方ならお分かりになると思いますが、借金の金額と固定費の高さにあります。
手術を行う場合には、高額な設備はもちろんのこと、手術を介助するスタッフも雇わないといけません。すると、借金と固定費がかなり高額になります。そして、手術をしてもらいたい患者さんがたくさん来るとは限りませんし、手術の間は一般の診療をする時間が限られてきますので、相対的な売り上げが減少してしまうと言うことにもなりかねません。
高額な医療機器を導入しないで開業をする方法
先生によっては、「高額な医療機器を導入したら、それが呼び水となって集患がしやすいのではないか?」とお考えの方もいらっしゃいます。私どもの経験上、経営リスクを考えると高額な医療機器はなるべく導入しない方が良いのです。
クリニックを開業するときは、高額な医療機器をなるべく導入しないような計画で、初期費用や固定費をなるべく低くして黒字化しやすい事業計画を立てます。そして、高額な医療機器は、必要性を感じてから導入を検討されたら良いと思います。
クリニックの開業時に高額な医療機器を導入し、その機器があまり活用されないようなことになれば、無駄になりもったいない話です。
また、医療機器を導入するとしても、新古品といった比較的安い値段のものも存在します。
高額な医療機器は、クリニック開業後に必要性を検討してから購入されても良いと思います。
特長のない診療科目「一般内科」での開業で失敗
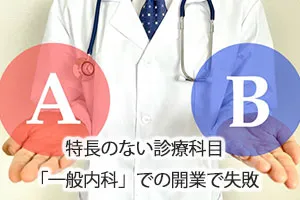
先生によっては、一般内科といった、あまり特長を出しにくい診療科目での開業を目指される方もいらっしゃいます。ところが、一番競合先が多くて特徴が出しにくい科目なので、集患には大変苦労します。
内科よりも特長のある診療科目で開業を
先生が、お寿司を食べに行きたいと思ったとしましょう。すると、何屋さんに行かれるでしょうか?
もちろんお寿司屋さんです。ファミレスでもお寿司を出してくれるところはありますが、ファミレスではなくお寿司屋さんを選ぶと思います。これを患者さんに当てはめてみましょう。例えば、アレルギーを診てもらいたい患者さんの場合は、アレルギー科クリニックと内科クリニックがあったら、どちらに行きたいと思うのでしょうか?
アレルギー科がお寿司屋さんに該当します。内科がファミレスに該当します。もちろん、ファミレスのお寿司は値段の割にそこそこの味ですが、「専門性の高いお店に行きたい」と思う人がほとんどだと思います。
内科クリニックといった、特長の無いクリニックを開業すると、集患がしにくいというリスクがあるのです。
それよりも、例えば「アレルギー科の専門だ」と標榜しておき、「皮膚科や呼吸器科も診ています」という付加価値を持っていた方が、患者さんから選ばれやすいでしょう。
女性専門の肛門科で差別化して開業された先生
過去に、女性専門の肛門科というニッチな診療科目で開業された先生がいらっしゃいました。
当初は消化器内科で開業しようとお考えでしたが、当社の開業コンサルティングで「この診療分野では、女性専門のクリニックが少ないので、1年ほど専門病院で研修を受けられ、開業されたらいかがでしょうか?」とアドバイスさせていただきました。
その先生は、当社のアドバイス通りに研修を受けたり、専門の先生から教えてもらったりして準備を重ね、1年後に開業しました。開業後は、黒字化には少し時間がかかりましたが、事業計画通りに手持ち資金を多めにストックしてもらっていたこと、ニッチさ故に口コミで患者さんが増えていき安定経営を実現されました。
自宅でクリニックを開業して失敗

自宅でクリニックを開業すると、「家賃を払わなくても良いですし、自宅が資産になる」ということで、一見すると失敗しにくいクリニックになりそうです。確かに、家賃を払いませんから固定費は大幅に下がると思います。
では、なぜ自宅でクリニックを開業すると失敗しやすいのでしょうか?
冒頭でご説明したことを思い出してください。クリニックが失敗するかどうかは、入るお金と出ていくお金が関係をしています。自宅でクリニックを開業すると、確かに出ていくお金は少なくなるのですが、入ってくるお金が大幅に減ってしまう可能性があるのです。
開業医である父親の自宅併設クリニックで開業した先生の失敗談
ある先生は、ご実家に父親のクリニックが併設されていたので、そこで開業することになりました。先生のお父様が開業医を引退される予定で、ご自宅併設のクリニックを息子さんが引き継ぐことに積極的でしたし、息子さんとしては生まれ育った家での開業で、父親のクリニックを引き継げることを喜びました。
40年以上使い続けられたクリニックは古びたものだったので、父親の手持ち資金でクリニックをリフォームし、息子さんの先生が家賃を父親に払うスタイルで、新しくなったクリニックにて開業されました。家主が父親なので、クリニックの家賃も安く済みますし、これまで来ていた患者さんも引き継げるというメリットがあります。
父親としては息子が帰ってきてくれるので、老後の面倒を見てもらえることを期待しました。また、家賃収入も得られることもあり、生活に困ることはありません。父親が若い頃は繁盛していたクリニックですが、父親も年齢を重ね、クリニックに来られる患者さんもお年寄りが増えてきました。父親は、「息子にクリニックを譲れば、また人が戻ってくるだろう」ということで、父親からすると良いことばかりのように思いました。
ところが、クリニックをリフォームし息子さんにクリニックを譲っても新規の患者さんが来ることは、あまりありませんでした。
父親が家主ですから、固定費は一般的なクリニックと比べて安く抑えられていますが、患者さんが来ないことには診療報酬が得られませんから、先生の手取り収入が下がってしまい、先生は悩んでしまいました。
そのような状態で当社にご相談いただいたのです。当社のコンサルタントからアドバイスは、「すぐに父親のクリニックを閉院させて、人通りの多い駅前などの繁華街で開業してください」ということでした。
なぜ自宅のクリニックは集患がしにくいのか?
失敗談でご紹介したご自宅は、閑静な住宅街の中のクリニックです。父親が開業した当時は新興住宅街で、人が移り住み始めた頃でしたから、駅前にも近所にもクリニックは存在しませんでした。ですから、自宅に看板をかかげたらそれを見て近隣に住む人達が大勢来てくれていました。
最近は、駅前の便利な場所にいろいろな専門性の高いクリニックが存在している時代です。
住宅街にあるご自宅に「内科クリニック」と看板を掲げても、近所の人にしか見てもらえませんから、新患さんの数も限られるわけです。今はスマホですぐにクリニックの場所を調べられる時代ですから、患者さんは便利な場所にある専門性の高いクリニックに受診することが一般的です。そして、駅前の人通りの多い場所に看板を出した方が、患者さんが来院しやすいのです。
そのようなことで、ご自宅で開業した場合には、住宅街にあり、なおかつ診療に特色がなければ、わざわざ患者さんが来院してくれる理由が薄れてしまうのです。
ご自宅で開業されて集患がしやすいパターンとしては、広い駐輪場や駐車場を併設したクリニックです。駅前には自転車が駐輪しにくいですし、小さな子どもを診療してもらうためには、駅前は不便です。それよりも、患者さんの自宅から近くにあり、なおかつ駐輪場や駐車場を併設したクリニックですと、患者さんが利用しやすいので集患がしやすくなります。
自宅をクリニックにしても資産になりにくい
自宅をクリニックにすることで、「資産が増える」とお考えの先生もいらっしゃることでしょう。そのようにご説明される開業コンサルタントもいると思います。しかし、実際のところ自宅開業のクリニックは、資産にはならずに負債になってしまうのです。
自宅のクリニックがなぜ資産とはならずに、負債になってしまうのかをご説明いたします。
そもそも資産とは、必要な時に直ぐに換金できたり定期的にお金が入ってくるもののことです。株式投資をすれば、その株を持っていたら配当が入ってくるようであれば資産になります。駐車場経営をしている場合であれば、そこに自動車を駐車してくれる人がいて初めてお金が入ってきます。反対にお金が出ていくもののことを負債といいます。
ご自宅である不動産を売ればお金にはなるでしょうが、自宅やクリニックがなくなってしまうことになりますので、現実には売却することのできない不動産であり、そのまま負債となってしまいます。
さて、ご自宅で開業されたクリニックはお金が定期的に入ってくるのでしょうか?
先ほどの事例では、お父様からすると自宅のクリニックは息子さんからの家賃収入があるので資産となります。ところが、患者さんの数が減ってしまって、「家賃が出せない」ということであれば投資をしたお金が返ってきませんから、負債になってしまうのです。
「息子だから支払いが出来ないことを許したが、誰か別の医師に貸したらどうか?」と考える先生もいらっしゃるかもしれません。息子さんではなく縁のない先生に貸すとしたら、どうでしょうか?
縁のない医師に自宅併設のクリニックを貸すことは勇気のいることです。借りる側の医師も、自宅併設のクリニックは借りにくいものです。そういったことから、借り手が付かないため、そのクリニックは負債となってしまうのです。
自宅にクリニック併設して開業することは、集患の目処がない場合は避けておいた方が良いです。
借金しないで自己資金だけの開業で失敗

医師によっては、手取り収入が高くなってくると、生活が派手になっていく人もいます。その反対に、バリバリと仕事に打ち込んで、「お金を使う暇がなかったから、いつの間にかたくさん貯まっていた」という先生もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのお金を使って、銀行などの金融機関から借金をしないで、自己資金だけで開業しようと考える先生もいらっしゃいます。借金をしないわけですから、それだけ経営が有利になり、リスクが減るというものです。確かにその考えは一理あります。ところが、借金をしなかったが故にクリニック経営を危なくする場合もあるのです。
借金しないでクリニック経営をした先生の失敗談
ある先生が借金をしないで、自己資金だけでクリニック開業をしました。テナント契約、内装工事、医療機器の購入など、8,000万円ほどを自己資金で出されました。そしてクリニック開業したときには自己資金をすべて使い果たしてしまいましたが、借金はゼロ円だったのです。
その先生は自己資金を使って開業しましたが、「患者さんが来るようになるまでに時間がかかり、その間にかなりのランニングコストがかかる」という予測は甘かったようです。開業支援を依頼したコンサルタントも、医療機器や医薬品などについては知識を持っていましたが、クリニック経営については素人だったようです。
クリニックを開業したら、立地条件にもよりますが、半年から1年くらいは赤字経営が続くことを想定しておいた方が良いのですが、見通しの甘い事業計画によって運転資金がショートしてしまい、経営が危なくなってしまったのです。
運転資金は余裕を持って確保しておくこと
クリニックが倒産する理由は、「患者さんから得られる診療報酬よりも出ていく費用が多くなり、赤字になってしまったとき」とお考えの先生は多いことでしょう。しかし、現実には赤字経営であったとしても倒産しないクリニックがあります。それは、運転資金を十分に持っているクリニックです。
クリニックが倒産する時は、赤字になったときではなく、運転資金が尽きてしまったときなのです。
運転資金が無くなってしまったら、雇っていたスタッフにお給料が払えませんから、スタッフは辞めていってしまいます。家賃も支払えず医薬品の仕入れもできなくなってしまいます。そういったことで、診療活動ができなくなり、クリニックの経営が成り立たなくなるのです。
そのように運転資金が尽きてしまって、必要な支払いができなくなることを、資金ショートといいます。
クリニックの開業を計画するときに立てる事業計画では、「診療科目とテナントの立地条件」によってどれくらい集患できそうかが予測できます。この予測の立て方が、実は開業コンサルタントのノウハウでもあります。この予測は絶対ではありませんが、経験がものを言います。
その経験に基づいてどれだけ患者さんが来院しそうかを想定し、黒字経営に至るまでに資金ショートを起こさないように余裕を持った事業計画を立てます。
借金してリスクを背負って開業した方が経営感覚を肌で感じる
クリニックを開業するときには、ほとんどの先生は金融機関から借金をされます。とは言うものの、無借金経営を目指すことは、とても良いことだと思います。当社では、自己資金は使うのではなく不足の事態に備えるための資金として確保しておいて、事業に必要な資金は借り入れでまかなうことをおすすめしています。
要は、借り入れした資金を返済できないような事業であれば、初めからやらない方が良いのです。
大きな借金をすると失敗した時に怖いという先生が多いのですが、なぜ借金をした方が良いのでしょうか?
それは、借金してある程度のリスクを背負って開業した方が、クリニックの経営感覚を肌で感じることができるからです。資金がショートすることでクリニックが倒産するわけですが、その根底にある考え方として、「甘い経営」があります。
経営は難しいもので、「最先端の医療技術を持っているから患者さんが来る」という単純なものではなく、「駅前に開業すれば患者さんが来る」というものでもありません。クリニックを開業したら、先生ご自身で幅広い医療技術を身に着けていくことはもちろんのこと、患者さんへの対応、利便性、PRの効果、資金繰りなどいろいろなことを全方位的に学び、考え、計画を立てて改善していくことが大切です。
それらの合計点が、競合となるクリニックに対して勝ることで、クリニックの経営が安定していくのです。
借金をすることで、その真剣さが増していくのですが、経営に対する真剣さが大切になります。
知識の偏ったコンサルタントに開業相談して失敗
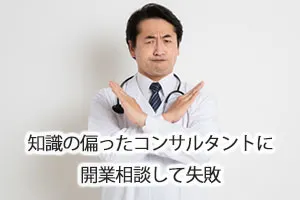
開業コンサルタントを名乗る人はたくさんいて、当社のようにコンサルティングを専門としている人もいれば、医療機器や薬品のメーカー担当者、税理士や会計士なども開業コンサルタントを名乗ることがあります。クリニックの経営では、「全方位的に学び、考え、計画を立てることが大切だ」とお伝えしましたが、コンサルタントによっては、アドバイスに偏りがある場合があります。
医療機器メーカーの営業担当に開業コンサルを依頼して失敗
ある先生が医療機器メーカーの営業担当者に開業コンサルティングを依頼して、失敗しそうになった事例をご紹介します。その先生は、当社にご相談いただき、事なきを得ました。
その先生がクリニックの開業をしようと考えた時に、たまたま出会った医療機器メーカーの営業担当者に相談しました。すると、「医療機器を私からご購入いただければ、無料でコンサルティングいたします」とのことで、承諾してしまったのです。
医療機器の営業担当者からすると、自分の営業成績になりますから、先生に高額な医療機器を進めたいところです。先生としては、コンサルティング費用が無料になりますし、どうせ導入しないといけない医療機器ですし、コンサルティング費用が浮いた分だけ色々な機器を導入できます。双方の利害が一致しての契約でした。
ところがクリニックの開業計画を進めていくうちに、先生が不信感を抱くようになりました。その理由はこうです。
まず、クリニックの開業場所を決める際に、明確なアドバイスがありませんでした。先生から「この場所はどうだろうか?」と相談したところ、どの場所も「いいですねー」という返事しかなかったそうです。
先生からすると、集患ができそうかを知りたかったのですが、どこでも良いから早く開業させて医療機器の購入契約をして欲しかっただけのようでした。また、医療機器に関すること以外のすべてのことは、別の業者に丸投げで明確なアドバイスもなく、初めて開業する先生に判断がすべて委ねられてしまったのです。
税理士に開業支援を依頼して失敗
また別の先生ですが、税理士に開業相談したケースもありました。税理士の専門分野は税務ですから、クリニックの開業ではありません。
税務については専門家なのですが、それ以外については素人同然と言える人が多いです。多少は開業に関する知識を持たれた方もいらっしゃると思いますが、クリニック経営はともかく、施設計画については知識の無い人がほとんどです。クリニックの事業計画を立てることはできたとしても、開業場所や内装工事、医療機器、資金調達といったことなど、理系の知識を含めたクリニック開業を全般的にアドバイスができることはありません。
ある先生からのご相談で、「税理士に開業相談をして半年ほど経ったけれども、まったく進まなかった」とご連絡をいただいたこともありました。当社がご支援させていただいたところ、その後順調に準備が進み先生のご希望通りの開業ができました。
このようなことから、クリニックの開業支援を依頼する場合は、当社のような開業支援を専門としている会社に依頼することをおすすめします。
クリニック開業支援で必要な知識とは?
クリニック開業支援で、先生が未経験の知識を補い、スムーズに開業準備を進め、クリニック経営を黒字に導き、いろいろなトラブルに対応できるためには、次のような全般的な知識が求められます。
- ・クリニックの事業計画や借入金の返済計画
- ・資金調達
- ・立地条件の検討やテナント契約
- ・使いやすく効率的なクリニックの内装設計
- ・建築基準法や消防法などの知識
- ・クリニック開業に向けた各種申請
- ・職員募集や人材育成
- ・クリニックのPR
- ・先生のライフスタイルのご相談(子育てと開業の両立など)
内装工事を見積もり金額の安さだけで選んで失敗
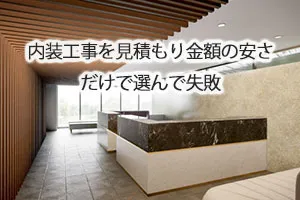
最後に、開業してから数年ほど経過して大規模な改修が必要となってしまった先生の失敗談をご紹介いたします。
当社に開業相談をいただき、全般的な予算計画などを立てて、当社での内装設計と工事をご提案させていただいたのですが、先生から「内装工事は安いところに頼みたい」と強くご要望されたので、そのようにして頂きました。その先生から、数年ほど経過して「オクスアイさんに内装工事を依頼しておけば良かった」とご連絡をいただきました。
その理由は、「打ち合わせや確認もなく壁を立て始めたり、電子カルテに必要なLANの配線が不足していたり、また開院からしばらくして水漏れが発生し、調べてみたところ配管の仕方が雑で、壁を壊して配管を大幅にやり直したり、工事全体が雑で安普請な仕上がりだった。」とのことでした。クリニックを開業してからたった数年で、大規模な修繕が必要となってしまったのです。
その先生はクリニックを1ヶ月ほど閉めて、内装の大規模な修繕を行いました。予定外の高額な費用がかかりましたし、水漏れで下の階のテナントにもご迷惑をかけてしまい、そこに保証もしないといけませんでした。また、1ヶ月間も閉めていたために、一部の患者さんも失ったと思います。
クリニックの開業では、高額な医療機器を導入しないようにしたり、テナント代がなるべく割安になるようにすべきであることを述べてきました。そちらの方が失敗しにくいクリニック経営ができるからです。しかし、テナントの坪単価は高いところで、なるべく坪数の小さなところを選ぶように、お金をかけるべきところにはかけて、不必要な箇所にはお金をなるべくかけないことが基本となります。
クリニックの内装でも同じです。見かけを華美にすることよりも、壁や天井裏の配管などの見えない部分に必要なお金をかけておくことで、開業してから20年以上にわたって快適に使い続けることができる内装工事をすることで、将来にわたり安定した経営ができるクリニックになるのです。
以上、さまざまなクリニック開業にまつわる失敗談とその対策をご説明いたしました。ここでご紹介した失敗談は、あくまでも事例であって必ずそうなるとは限りません。条件によっては、同じような場合でも安定した経営ができる可能性もあります。
病気の治療にセオリーがあるように、クリニックの開業や安定経営にもセオリーがあります。出来る限りそのセオリーに沿って物事を進めた方が、失敗しにくいことが知られています。クリニック開業コンサルタントを選ぶときは、全方位的にアドバイスをしてくれる能力があるかどうかが明暗を分けることになります。
できましたら、当社にご相談していただければ良いのですが、当社では東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県での開業を中心に支援しておりますので、残念ながらこの記事を読まれた先生方全員をご支援することができません。そこで、当社ではこうしたコラムで開業を成功するための沢山のノウハウを公開しているので、それをしっかり学んでいただければと思います。
関東圏で開業をお考えの方で、当社のコンサルタントの話を聞きたい方は、ぜひオンラインで無料開催しているクリニック開業Webセミナー&個別相談会にお申込みください。そこでは、失敗しない開業をしつつ先生の手取り収入を最大化できるミニマム開業のご説明や、先生の開業に関する悩み事の相談にも幅広く対応をしています。
悩める先生方のご相談をお待ちしております。



