クリニックの開業場所でほぼ決まるクリニックの経営リスク
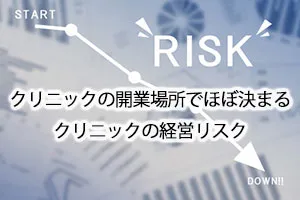
クリニックを開業した場合には、さまざまな経営リスクがあります。近年、クリニックの数が増えていますから、「近所に競合となるクリニックが開業してしまって患者さんが来なくなる」というリスクは多いです。
開業をお考えの先生は、「低リスクで開業したい」とお考えのことと思います。そして、低リスクの開業方法は、開業場所でほぼ決まるということをご説明したいと思います。
なぜ、クリニックの開業場所によって経営リスクが異なるのか、低リスクとなる開業場所はどういったところなのかをご説明しますので、開業場所を探す際の参考になさってください。
クリニックの開業場所と経営リスクの関係
最初に、クリニックの開業場所と経営リスクの関係をお話しいたします。
固定費と変動費

経営リスクを解説する前に、固定費と変動費についてご説明します。クリニックを経営するときにかかる費用は、固定費と変動費に大別できます。
固定費とは、患者さんを診察する人数に関係なく、毎月かかる費用のことです。例えば、テナントの家賃やスタッフさんの人件費、水道代や電気代などの水道光熱費、雑誌などを定期購読していたらそれらも固定費になります。
固定費は厳密には、患者さんが少ないシーズンや休みの多い月は非常勤のスタッフさんに多く休んでもらったり、電気もそれほど使用しないので、「患者さんの来院が少ないときは少しは安くなるから、変動費になるのではないか?」と思われるかもしれませんが、1年間を通しての月平均で固定費として事業計画を立てることが多いです。
変動費とは、患者さんを診察する人数に応じてかかる費用のことです。例えば、患者さんに使用する医薬品や注射器、衛生材料、診療材料などといったものです。患者さんが多くなればそういった診療材料などをたくさん使用するので、費用も多くかかります。反対に患者さんが少なければ、費用が低くなります。そのように患者さんの数で変動するので、「変動費」といわれています。
固定費が高いと経営リスクが高まる
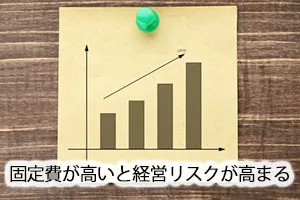
クリニックの経営リスクは、借金の多さだけではありません。借金が少なかったとしても、患者さんがあまり来ないクリニックでは、経営状態が赤字になってしまい、資金が底をついてしまったら倒産です。
診療をして得られた診療報酬の金額と、固定費と変動費の合計の出ていくお金を差し引いて資金がプラスに計上ができると黒字経営と言えます。ですので、経費が多くかかったとしても、安定的に集患ができたら経営も安定します。
しかし、集患の状況は変動するものです。安定して集患ができていたとしても、いきなり近所に競合クリニックが開業してしまったら、患者さんを半分取られてしまう可能性もあります。
患者さんが半分に減ってしまったら、変動費は半分になりますが、固定費は患者さんの数に関係なく一定金額がかかってしまいます。ですから、固定費はなるべく安く、なおかつ集患がしやすい場所で開業することが大切です。
ときどき開業をご希望の先生から、「自宅で開業をしたら固定費が安くなるし、資産になるから良いのでは?」とご相談いただくことがあります。それはまったくの誤りです。自宅開業は確かに固定費を下げることにつながりますが、集患ができないなどの問題で高リスクとなる場合があります。ご自宅での開業について、後ほど解説いたします。
集患と固定費の関係

集患がしやすい場所での開業ということは、駅前や商店街といった人通りが多い目立つ場所を開業場所に選ぶことです。
ここで、「駅前で開業したら家賃が高くなって、固定費が高くなるではないか」とお考えの先生もいらっしゃることでしょう。その通りなのですが、少し解説を付け加えます。
確かに駅前は、駅から離れて人通りの少ないところと比べたら家賃が高くなりますが、それは「坪単価が高い」のです。坪単価とは、1坪当たりの家賃の単価のことです。坪単価の高いテナントであったとしても、坪数が小さいところであれば、家賃の総額は高くなりません。そして、集患がしやすい場所であるため、クリニックの経営は安定しやすくなります。
これまで開業支援をさせていただいたクリニックでは、早ければ2ヶ月目で黒字になったところもありました。開業方法によっては、1ヶ月目から黒字にすることも可能です。
まとめると、クリニックを低リスクで経営するためには、固定費が低く抑えられる場所で開業すること。そして、駅前などの坪単価が高い場所で、坪数が小さい場所に入居することです。
開業時は高額な医療機器をなるべく入れないこと
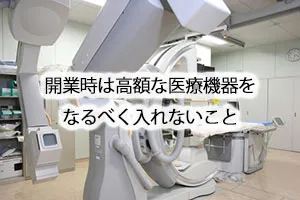
駅前の坪数が小さい場所で開業することで、集患がしやすく黒字化させやすいことが判りました。ここで、「坪数の小さな場所で開業したら、必要な医療機器が入れられないじゃないか」と思われる方も多いと思います。確かにその通りです。
先生によっては、病院勤務のときに使用していた医療機器をそのまま全部導入して、いろいろな診療ができるようにして開業したいと思う方もいらっしゃいます。しかし、たくさんの医療機器を導入したら、その分だけ借金の金額が増額することになりますし、スタッフの人数も増やさないといけませんし、広いスペースの家賃も支払わなくてはなりませんので、固定費が増大してしまい経営リスクが高くなってしまいます。
低リスク開業を目指すのであれば、医療機器は必要最小限のものに限って導入しておき、クリニックを開業してから需要を確認して必要性を検証してから導入しても遅くはないのです。もし最初から導入した医療機器が「あまりニーズが無くて、ほとんど使用しなかった」ということになってしまうと大変もったいない話です。
患者さんが増えて、現状のクリニックでは手狭になってきて、「坪数の小さなクリニックではそれ以上の発展が難しい」ということになったら、近所の広い場所に移転したら良いと思います。すでに患者さんがいる状態で、そのニーズを感じての移転拡大であれば、新たな設備投資をしても低リスクと言えます。
さらなる低リスク開業で高い手取り収入を得る方法

クリニックの開業場所を駅前などの人通りの多い場所で小さなテナントに入居し、なおかつ高額な医療機器を導入しないようにして開業をすることで、低リスクな経営ができることを述べました。さらに付け加えるならば、次の3点が重要となります。
- 1. 診療報酬を年間5,000万円以下に抑えること
- 2. スタッフをパートさんだけにすること
- 3. 医療機器の操作や採血を先生が自分でできるように練習しておくこと
これらの条件をすべて満たすことができたら、低リスクでなおかつ先生の手取り収入を最大3,000万円ほどにすることも可能です。その場合、先生が働く時間は、従来型の一般的な開業をした場合の半分くらいになるでしょう。
そのポイントは、「租税特別措置法第26条(特措法)という法律を活用すること」です。
この法律は、「診療報酬が年間で5,000万円以下であれば、その金額の約70%を経費として認める」というものです。例えば、5,000万円の売上高であれば、その70%ほどの約3,500万円を経費として認められます。その差額の約1,500万円を所得として確定申告するので、税金は約400万円ほどになり、まずは約1,100万円くらいが手元に残ります。
そして、経費として認められた約3,500万円ですが、ミニマム開業の場合には実際には3,500万円も支払うことはありません。例えば、家賃や光熱水道費などで合計600万円、人件費が600万円、変動費が400万円としたら、合計1,600万円が実際に支払われた金額となります。概算経費と実際にかかった経費の差額の約1,900万円を先生の手取り収入として良いと特措法に定められています。
税務申告で残った約1,100万円と、概算経費と実際の経費の差額の約1,900万円を足すと、約3,000万円が先生の手取り収入となります。
このように特措法を活用することで、低リスク開業をしながら、先生の手取り収入を増やすことができるのです。このような開業方法を、「ミニマム開業」といいます。
仮に同程度の手取り収入を、特措法を活用しないで得ようとした場合には、おおよそ1億円ほどの売上高を上げる必要があります。つまり特措法を活用したときよりも、2倍以上の仕事量をこなす必要があります。
ミニマム開業は、家族のために使う自由な時間をつくりながら高い手取り収入も得られるので、子育てとキャリアを両立したい女性医師や、親御さんの介護をしないといけなくなった医師にとっては理想的な開業方法です。
自宅開業での経営リスク

さて、先ほど自宅開業ではリスクが高いことを述べましたが、その理由をご説明したいと思います。
自宅での開業は、一見すると低リスクのように思います。なぜなら、テナントを借りることをしないために、家賃を払わないで済むので固定費をかなり下げることができるからです。また、自宅を改装して診療所が付属するわけですから、資産が増えるように思います。固定費が下がり、資産が増えるということで、低リスクと感じるわけです。
患者さんが来ないリスク
1つ目のリスクとして、患者さんが来ないリスクがあります。自宅開業では、その周辺に先生が診療する科目のクリニックが他に存在しなければ、患者さんがクリニックを探して来てくれるかもしれません。
ところが、自宅の開業では看板を見て来てくれる人は近所に住んでいる人だけで少ないですし、インターネットでクリニックを探す患者さんは、やはり便利なところにあるクリニックを利用することになります。また、もし競合がいない診療科目であったとしても、駅前などの立地の良い場所に同業のクリニックができたら、患者さんにとっては、「買い物ついでや通勤のついでに通うことができるので便利だ。」ということで、駅前のクリニックを利用するようになってしまいます。
小児科のように、自転車が停められて、なおかつ自宅から近い場所にクリニックがあったら、通ってくれると思いますが、その他のクリニックではやはり駅前といった目立つ場所にあった方が集患には都合が良いです。
自宅併設の診療所は資産にならないというリスク
資産とは、自分自身にお金が入ってくるもののことです。例えば、駐車場経営では契約してくれた人がいたらお金が入ってきますから、それによって資産となるわけです。もし、駐車場経営で「お客様がゼロ」であれば、草むしりのメンテナンスや固定資産税などといった費用が出ていくだけですから、駐車場を持っていたとしてもそれは負債になります。
では自宅併設の診療所はどうでしょうか?
まず患者さんが少ない可能性が高いということ。そして、診療所と自宅が併設されているので、引退後に誰か不特定の医師に診療所を貸すことが難しいこと。これらを考慮すると、負債になってしまう可能性が高くなります。
自宅併設の診療所は、実は資産になるのではなく、「固定資産」になるだけなのです。そして固定資産を維持するためには費用が必要となり、トータルで負債となってしまうことが多いのです。
以上、クリニックの開業場所と経営リスクの関係について解説しつつ、ミニマム開業の魅力や自宅開業をおすすめしない理由もご説明いたしました。
まとめると、クリニックの開業場所は駅前などの人通りが多い場所で、なるべく小さな坪数のテナントを借りて開業すること。場所の良いビルでは1階だと家賃が高いので、同じビルの2階よりも上の階層を選ぶことです。
そして、できるだけ高価な医療機器は導入しないで最低限にしておき、費用を安く抑えること。医療機器の導入は、必要となった時に検討することです。
また、それらの開業方法であれば、診療報酬を5,000万円以下に抑えて、特措法を活用し、手取り収入を増やすことができます。
独立して開業医を目指される先生が最初にしなくてはならないことは、開業コンサルタントの支援で事業計画を立てることです。低リスクの開業を行いたい場合には、ベテランのコンサルタントといっしょに入念な事業計画を立てることが大切です。初めて経験するクリニック経営でも、事業の見通しが立ち、安心して開業に進むことができます。
クリニックの事業計画や開業場所のアドバイスなど、開業に関する各種ご支援ならオクスアイにお任せください。
まずは、低リスク開業を解説する無料Webセミナー&相談会にご参加ください。



