院長が時短勤務しても黒字化できる低リスクのクリニック開業方法とは?
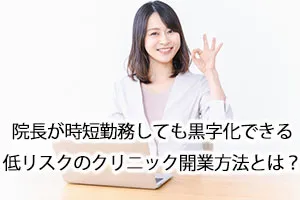
時短勤務とは、病院やクリニックに勤めている医師や看護師さんが、育児や介護といったご家庭の事情で勤務時間を短くして働くことができる勤務形態のことです。
小さなクリニックの場合、そういった制度を設けていたとしても、院長先生ご自身は、時短勤務をするわけにはいかないことが、一般的です。そのため、「クリニックを開業したら、院長先生が率先して働かないと、クリニックが黒字化できない」と思われることと思います。
実際に、当社にて開業コンサルティングをしてきた中で、ご相談いただいた先生方の多くは、そのようにお考えでした。
ところが、院長先生ご自身が時短勤務をして、休みたいときに休んだとしても、低リスクで黒字化ができているクリニックもあります。そのような独特な経営スタイルでも開業ができてしまう方法を、「ミニマム開業」といいます。
この記事では、「自分のクリニックで時短勤務をしたい」とお考えの先生に向けて、ミニマム開業をされた先生の事例や、ミニマム開業とはどういった開業方法なのか、手取り収入はどれくらいになるのかといったことをご説明いたします。
医師を雇うとクリニックの倒産リスクが高くなる

院長先生ご自身が時短勤務をしようとすると、一般的なクリニックの開業方法では、勤務医を雇い自分が休むときに代診として入ってもらいます。
勤務医を雇ったら、支払うお給料が高くなりますから、それだけ経費が多くかかってくるので、その分だけの売上を得なければなりません。しかも、自分が休みたいときに合わせて勤務してくれるような、都合の良い働き方をしてくれる医師はいませんから、シフトを決めて雇うことになるので、それだけ支払うお給料も高くなります。
また、ずっと先生がいるようなクリニックでは、スタッフを何人か雇うことになります。スタッフも休みたいときがある訳ですから、予備の人員も含めて雇うことになります。
そのような体制を取ると入居するテナントもある程度の広さが必要となりますので、テナントの家賃も割高になってきます。
勤務医やスタッフさんに支払うお給料は、患者さんがたくさん来てくれる月も、あまり患者さんが来ない月も、固定費として一定の金額がかかってくるので、それだけ経費が出ていってしまいます。クリニック経営を黒字化するためには、ご自身や勤務医、スタッフのお給料や社会保険料などに加えて、テナント代や光熱費といった費用を合わせた金額よりも、多くの売上高をあげることが求められます。
経費がたくさんかかり、それを賄うためにたくさんの売上高をあげないといけないクリニックは、リスクの高い経営状態だと言えます。患者さんが減ってしまったら、赤字になりやすいからです。そういったクリニックでは、院長先生は気が休まらないでしょうから、時短勤務どころではありません。
時短勤務で開業ができた院長先生の事例ご紹介
時短勤務で開業し、しかも黒字化ができているクリニックの事例を2件ご紹介します。
週3日、しかも午前中だけの時短勤務ができるクリニック
1件目の事例は、「自分は体力が無いので、週3日だけ、しかも午前中だけ働けるクリニックにしたい」ということで、クリニックを開業させた女性医師の事例をご紹介いたします。
クリニックを週3日だけ、しかも午前中だけですから、週に9時間しか開業しないクリニックです。一般的には、「そのような開業で黒字化は無理だ」と考えることでしょう。そのようなことが果たして可能だろうかとご自身でも疑問に思いながら、当社にご相談いただきました。
そのご相談には、もちろん「可能です」と即答したわけです。
先生は子どもの頃から体力に自信がなく、それでも持前の熱意で医師になられましたが、出産後に通常の勤務が難しいほどに体力が落ちてしまわれました。一時期、臨床から離れようとも考えられたそうです。しかし、本当に自分のやりたいことを考えた末に、当社にご相談に見えました。
当社の開業コンサルティングでは、週9時間の勤務でも黒字になるような事業計画を立て、先生のご要望の場所にて女性専門の精神科クリニックを開業されました。開業後は、ご自身の体調と子育てを優先して時短勤務をしつつも、黒字経営のクリニックにされました。
この事例の詳細は、こちらのページをご覧ください。
子育てをしながら都合の良い時間に開業して黒字化できるクリニック

結婚をして出産した勤務医の女性医師は、お子さんと一緒に過ごす時間の確保の難しさを感じます。子どもは急に熱を出したり、学校から呼び出されたりすることもあります。受験の年齢になってくると、お子さんのサポートのために接する時間も多くなってきます。
2件目の事例の女性医師は、「子育ての時間を取りたいけれども、勤務医では難しいから開業したらいいのではないか?」と同級生の女性医師からアドバイスをもらい、当社にご相談がありました。
先生の診療分野は内科・消化器科だったのですが、開業をご希望される場所は都心に近いこともあって、内科・消化器科クリニックでは集患が難しいため、「女性専門の肛門科」をご提案させていただきました。開業はすぐにはできませんから、それまでの1年間ほど、肛門科の専門病院で経験を積まれました。
開業後は、子育てをしながら都合の良い時間に予約制で患者さんを診るようにされました。専門性の高さが功を奏し、比較的早く黒字化ができました。
この事例の詳細は、こちらのページをご覧ください。
子育てとクリニックの開業を両立させたいとお考えの先生は、「子育てと両立できるクリニックの開業方法とは?女医の人生設計」もご参照ください。
時短勤務でも黒字化ができる開業方法のポイントとは?
院長先生が時短勤務をしても黒字化ができ、なおかつ低リスクという条件で開業をするためには、ミニマム開業が最適です。ここではミニマム開業のポイントについてご説明します。
1.テナントは坪単価が高く坪数は小さい駅近で

クリニックの黒字化は集患ができるかどうかによりますが、そのためには立地条件の良さが大切です。立地条件が良い場所とは、集患がしやすい場所ということですが、そういった場所は誰もが開業したい場所ですから、当然坪単価が高くなります。
坪単価とは、1坪当たりの家賃のことです。坪単価とテナントの坪数を掛けた金額が、テナントを借りたときの家賃となります。テナントの家賃は、坪単価で決まるのではなく、坪単価と坪数を掛けた金額で決まります。ですから、坪単価が高い場所であったとしても、坪数が小さなテナントであれば、家賃の総額は低くなります。
一般的に、「坪単価の高い場所は集患がしやすいけれども、家賃が高い」と思われがちですが、面積の小さなテナントを借りることができれば、それだけ黒字化がしやすいクリニックになります。
2.自己資金を貯めておくこと
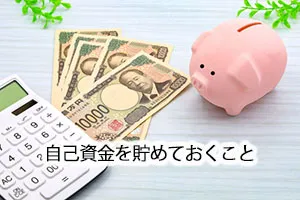
クリニックの開業コンサルタントに相談すると、「自己資金がなくても開業はできます」と言われることがあります。それは全く嘘とは言えないのですが、実はリスクの高い方法なので、自己資金がある程度あった方が有利に開業することできます。
どのように有利かと言いますと、それは条件の良い物件に巡り合ったら、すぐに契約ができると言うことです。そのある程度の金額とは、具体的には、都心での開業であれば1,000万円ほど、郊外であれば500万円程度です。
テナント物件は、早く申し込んだ順に審査があり契約相手が決まります。そして契約をするときには手付金として、1ヶ月分の家賃と敷金が5~10ヶ月分程度必要です。それらの契約金をすぐに支払える人が契約できます。立地条件の良い物件は、誰でも入居したいわけですから、募集をすればすぐに契約が決まってしまいます。そのためのお金を、自己資金として持っておくことが大切なのです。
もし自己資金が無ければ、それを銀行などの金融機関から調達することになりますが、資金調達のタイミングは「テナントの契約をしてから」になることがほとんどです。ですから、自己資金があれば立地条件の良いテナントに確実に入居が可能となるのです。
3.医療機器は必要最小限で
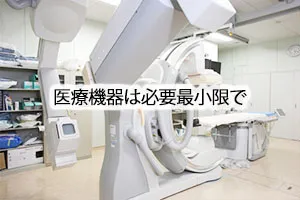
小さなテナントで家賃が安ければ、それだけ毎月出ていく費用「固定費」が安く済みます。そして、小さなテナントですから大がかりな医療機器が導入できませんし、必要最小限で抑える決心ができます。
先生によっては、「あの診療もしたいから、この機器も必要だ」ということで、いろいろな医療機器を取りそろえようと考える方がいらっしゃいます。いろいろな医療機器を取りそろえることができたら、それだけ多くの患者さんを集患できるように感じますが、あまり利用しない医療機器を抱えることになるので、初期投資金額が大きくなってしまうのです。
初期投資金額が大きくなると、それだけ返済金額も大きくなるわけですから、リスクの高いクリニック経営になってしまいます。
リスクの低い開業をするためには、小さなテナントで集患がしやすい物件を借りて、医療機器を必要最小限で抑えることが大切です。医療機器は、開業後に必要性を感じてから導入しても良いのです。
さらには、当社のコンサルティングをご利用いただいた場合には、医療機器のメーカーに相談して、展示会などで利用された新古品を安く導入できる場合もあります。
4.完全予約制にする
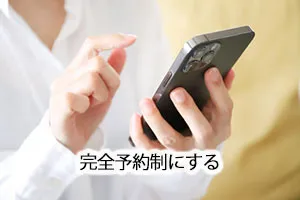
自分が休みたい日時に合わせてクリニックを休診できるように、予約制を活用します。休みたい日があれば、あらかじめ予約システムを設定しておいて、患者さんが予約できないようにします。すると、院長先生が休みたいときに休める時短勤務ができるクリニックができます。
クリニックの予約システムも、オンラインサービスで手軽に操作できるものもありますから、ご自宅や出先でも予約状況を確認したり、患者さんに連絡を取ったりすることもできます。
最近開業するクリニックでは、キャッシュレス決済の導入をお勧めしています。すると、現金のやり取りがなくなるので、事務スタッフの手間を大幅に削減することができます。
5.受付スタッフはパートタイマーで働いてくれる人を1名のみ
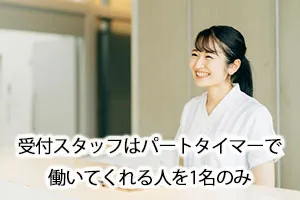
小さな面積のクリニックでは、医療機器は少ないですし、予約制であれば新患さんが突然に来院することも少ないでしょうし、キャッシュレス決済で現金の扱いも少なくなるので、事務スタッフはパートタイマーで働いてくれる人が1名だけ受付にいれば済みます。
子育てをするための時短開業であれば、同じように子育てをしているパートタイマーのスタッフさんを雇うことができます。一般的なクリニックでは、子育てをしているパートタイマーさんでは急に休むことが難しいです。ところが、院長が自ら時短勤務をするクリニックだと、パートスタッフさんもお互いにシフトの調整をすることで気兼ねすることなく休むことができます。
「受付スタッフが1名で、クリニックの運営ができるのか?」とご心配になる先生もいらっしゃいます。それもそのはずです。今まで勤務していた病院では、たくさんのスタッフがいて、いろいろな業務が存在していたわけですから、「自分でクリニックを開業したら、いろいろな事務業務が発生する」とお考えのことと思います。
ところが、租税特別措置法第26条による概算経費を適用することで、経理業務を大幅に軽減できます。この法律を活用すると、保険診療が年間5,000万円までの場合に、およそ7割を事業の経費として認めてもらえるので、税務署への申告は保険診療でえた金額の3割を所得として申告するだけです。そのため、経理の帳簿を作成する必要もなく税理士に顧問を依頼する必要もありません。
ミニマム開業の時短勤務での手取り収入はいくら?
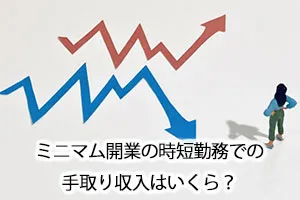
院長がミニマム開業で時短勤務をしたときの手取り収入がどれくらいになるのか試算したいと思います。
例えば、保険診療が年間2,000万円だったとしましょう。この金額は、週に3日ほどしか働かなくても得られる金額だと思います。
家賃や光熱費が月30万円で年間360万円、スタッフの人件費が200万円だったとします。医薬品などの変動費は、診療科目によって異なりますが、ざっくりと200万円かかったとしましょう。すると、合計で720万円です。
2,000万円から720万円を引くと、1,280万円が残ります。一般的には、利益となる1,280万円に税金がかかります。
税務署に申告するときは、租税特別措置法第26条を活用しますから、2,000万円のうち、その7割である1,400万円を概算経費として申告できます。そうすると、1,280万円に税金がかかるのではなく、概算経費を引いた600万円に税金がかかりますから、税金が半額以下に下がります。
さらには、実際にかかった経費720万円と申告をした1,400万円の差額である680万円は、院長先生の手取り収入として良いわけです。すると、概算で手取り収入は1,000万円を超えてきます。
このようにして、院長先生が時短勤務をして、子育てや親の介護といった時間に割いたとしても、充分な手取り収入を得ることができます。租税特別措置法第26条を活用しての手取り収入は、勤務医をしていたときと比べて半分くらいの量を働いたとしても、最大3,000万円ほどにできます。
以上、先生がクリニックを開業して時短勤務をしても十分に黒字化ができ、手取り収入も大きくなり、なおかつリスクも低い開業方法をご説明いたしました。
ここでご紹介した内容が、「本当のことだろうか?」とか「もっと具体的に教えて欲しい」ということであれば、当社が開催している無料Webセミナー&相談会にご参加ください。院長先生ご自身が時短勤務をして黒字化できるための方法を、開業コンサルタントが丁寧にご説明いたします。
ご連絡をお待ちしています。



